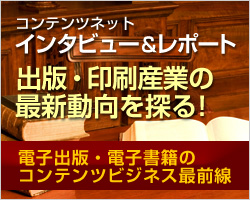ニュースリリース
2023.07.12
◆モリサワ 2023年度新書体として「欅明朝 Oldstyle」や「ボルクロイド」「プフ サワー」など個性派が揃う 16ファミリーをリリース
株式会社モリサワ(代表取締役社長:森澤彰彦 本社:大阪市浪速区敷津東2-6-25Tel:06-6649-2151 代表、以下モリサワ)は、2023年秋にリリースする新書体の一部を発表する。広告や動画テロップなど、印象的な見出しに映えるデザイン書体を多く取り揃えた、個性豊かな16ファミリーになっている。
広告やコミック、ロゴなどの目を惹きたいシーンには、パワフルでエッジの効いた作風の「ボルクロイド」、ミステリアスな意匠の「月下香(げっかこう)」、幾何学的な骨格に丸みのあるエレメントを組み合わせた「アルデオ」、そして可愛らしい太ゴシック風デザイン書体「つぶてん」が個性を発揮する。
オールドスタイルの書体である「欅(けやき)明朝 Oldstyle」、「欅角ゴシック Oldstyle」は、金属活字由来の骨格や自由な運筆のかなが、上品でやわらかい印象を生み出しています。それぞれ2ウエイトをご用意し、使いやすさにもこだわっている。
また、統一しすぎない自由な字形と小さめの字面が昨年好評だった「プフ」シリーズから、新たに「プフ サワー」、「プフ ソワレ」をリリースします。レトロな可愛さやキャッチーな明るさの表現が得意な書体である。
近年、モリサワは台湾の繁体字フォントをベースにした書体開発に取り組み、重層的な文字文化を取り入れたデザインを編み出している。「美風(みかぜ)」は、台湾の玉川設計所が手掛ける繁体字フォントをベースに制作され、涼やかで洗練された雰囲気をまとっている。また、台湾の子会社であるArphic Typesの書体の漢字を組み合わせた「翠流(すいりゅう)きら星」と「翠流ゆゆポップ」は、遊び心やホッとするような優しさを伝えるのに適したデザイン書体である。
「瓦明朝」は毎日新聞社が開発した、モダンテイストの明朝体。横画やハライの先端が太めに設計されており、視認性が高いことが特徴。さらに、品位や信頼感がある太楷書体として「史仙堂(しせんどう)楷書体」もお目見え。賞状や証書はもちろん、各種商品パッケージや、目を惹きつける見出しなど大きなサイズでの使用におすすめである。
そして和文書体以外にも、欧文フォント「Lutes UD PE」の多言語展開としてThai / Arabic / Devanagari(デーヴァナーガリー)が新たに加わる。「Lutes UD」シリーズは、デジタルデバイス上での視認性に配慮し、ローコントラストかつクリアですっきりとした印象のセリフ体。各言語の文字の特色を活かしながら、本シリーズで多言語を展開することにより、デザインの一貫性を持たせることができる。
モリサワ公式note
「2023モリサワ新書体情報解禁!個性派揃いの今年のラインナップを一挙ご紹介します!」
https://note.morisawa.co.jp/n/n0a99ce535239
2023年の新書体は、かねてより要望の多かった人気書体のウエイト拡張も予定している。
Morisawa Fonts
MORISAWA PASSPORT 製品 (※1)
MORISAWA Font Select Pack 製品
Webフォントサービス TypeSquare
■提供時期
2023年 秋
(※1)MORISAWA PASSPORTへの新書体搭載は、2023年分をもって終了する。以降の利用はMorisawa Fontsへ移行。
詳細は(https://www.morisawa.co.jp/products/fonts/passport/migration/)
MORISAWA PASSPORTのサービス終了予定のお知らせ以前に複数年で契約され、現在も利用中のユーザーに、新書体サポートプログラムを実施予定である。対象条件などの詳細は(https://www.morisawa.co.jp/about/news/9507)を参照。
※記載されている内容は、予告なく変更する場合がある。
●Morisawa Fontsへの契約移行に関する問い合わせ先
[MORISAWA PASSPORTご契約者様向け] Morisawa Fonts 移行サポートサイト
https://mf-migration.morisawa.co.jp/hc/ja
●同件に関する問い合わせ先
株式会社モリサワ 東京本社 ブランドコミュニケーション部 広報宣伝課
E-mail:pr@morisawa.co.jp
SNSでも最新情報を公開している
Twitter:@Morisawa_JP
Facebook:@MorisawaJapan
※記載されている内容は、予告なく変更する場合がある。
※記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標である。
2023.07.09
◆富士フイルムグラフィックソリューションズ Revoria Press PC1120導入事例――株式会社井上総合印刷 多彩な特殊色と機動力の高さを活かし、新たな付加価値の提供を目指す 発想が広がり、現場のモチベーションアップにも大きな効果
1966年の創業以来、“共存共栄の精神”を大切に、栃木県で地域に根差した事業を展開する井上総合印刷(本社:宇都宮市岩曽町1355番地、代表取締役社長:井上加容子氏)は、2020年の『Jet Press 750S』に続き、今年3月、トナー機の新戦力として『Revoria Press PC1120』を導入し、デジタル印刷の生産体制の強化を図った。持ち前の発想力と企画力で、これまでもさまざまなアイデアを生み出してきた同社が、最新POD機をどのように活用し、どんな価値を提供していくのか。井上社長に、導入の背景や現時点でのメリット、そして今後の活用戦略などを伺った。

井上総合印刷は、宇都宮市内に本社工場と2つのオフセット印刷・製本加工の工場、東京都内に営業所を持ち、商業印刷物のほか、図録や記念誌、写真集、ノベルティ、自費出版の書籍などを幅広く手がける。また、『ミウラ折り』のライセンスを取得し、印刷・折り加工から管理まで一貫して行なえる体制を確立しているのも特色の一つだ。印刷の枠を超えた地域振興活動にも積極的に取り組んでおり、2017年にレンタルスペース&カフェ『Cafe ink Blue』を宇都宮市内中心部に開設、2020年には観光地支援の一環として、観光名所である大谷石採掘場跡地に『そば倶楽部稲荷山』をオープンさせた。

井上社長
デジタル印刷については、Jet Press 750Sと、Revoria Press PC1120を含むPOD機3台を本社工場に配置し、優れた機動力と高品質・バリアブルといった特徴を活かした多彩な提案を行なっている。その成果もあり、コロナ禍の影響や、原材料費や物流費・光熱費の高騰といった厳しい環境下でも、堅調に受注を得ている。井上社長は、昨今の市場ニーズの傾向についてこう語る。
「単に情報を伝えるだけの印刷物というのは、かなり厳しい状況になってきていると感じます。この傾向は以前から続いていますが、コロナ禍で拍車がかかり、加えていまはあらゆるものの値段が高騰しているので、情報を伝えるだけの手段としては、紙はますます選ばれにくくなってきています。ではどんな『紙』なら必要とされるのかと考えると、たとえばパッケージやオリジナルカレンダーなど、広告宣伝やビジネス書類とは違った『機能』を持ったモノとしての紙が注目され始めているように思います。つまり『それ自体を使える印刷物』。そしてそこにお金を出すからには、デザインや形状・素材などにもこだわりたいという方も増えていると感じています」
飲食店などで使われる紙マットや油避けの紙など、いままで「機能だけが求められていた紙」に、新たに付加価値をつけたいといった印刷需要も増えているという。
「これから、『多少高価でも付加価値の高いモノを』と考える方がもっと増えてくると思います。そうしたお客さまの価値観にどれだけマッチした商品を創り出せるかが大事ですね。いま、多くの企業が『いかにコストをかけずに商品を売るか』ということを考えていますが、本当に価値を伝えたいとか、高級なものを売りたいというときには、Webやメールではなく紙の印刷を選ばれるお客さまが多いので、そのニーズに対してどんな提案ができるか。そこがデジタル印刷機の重要な使いどころにもなってくると思います」

本社工事に設置されたRevoria Press PC1120。付加価値創出の要となる新戦力だ
■機械の設計面でもサポート面でも、信頼性の高さを確信
同社では現在、Jet PressとPOD機3台を、オフセット印刷機とカラーマッチングを図った上で、仕事内容に応じて使い分けている。Jet Pressは、B2サイズ対応・高画質・バリアブルといった特徴を活かしてコロナ禍でも新たな需要の創出に活躍してきたが、井上社長は、これからの印刷需要を考える中で、より小回りが利き、かつ高い付加価値を生み出せるデジタル機が必要だと感じていたという。
「ちょうど、PODの主力機であったColor 1000 Pressが入れ替えの時期を迎えていたこともあり、他社機も含めて新たな機種の検討を進めていました」
付加価値提供の観点から、シルバーやゴールドなどの特殊色の使用を前提として選定することに。複数のメーカーからプレゼンを受け、実機デモも確認し、さまざまな角度から検討した。
「最終的にRevoria Press PC1120に決めた理由は、機械と人への信頼ですね。まず機械の信頼性については、これまでいろいろなメーカーのPOD機を見てきているので、蓋を開けて内部構造を見せていただくとだいたいわかるんです。その点、PC1120は、大事な部分をしっかりとつくり込んでいるというのが一目瞭然でした。開発担当の方のプレゼンも、非常に熱意がこもっていて、プリンターの延長ではなく生産機として考え抜いてつくられているということが、はっきりと伝わってきました」
もちろん、井上総合印刷にとって重要な戦力となる設備である以上、感覚的な判断だけでは決められない。
「出力品質については、私の独断ではなく、できるだけたくさんの目で検討しようと。最終的に候補に残った2社のメーカーさんに同じデータを同じ日に出力していただき、名前を伏せて印刷オペレーターやデザイナー、企画スタッフに見てもらって投票させたんです。結果、圧倒的にPC1120の方がいい! ということになりました。やはり、情熱を込めてつくられているだけの良さが、品質にも表れているのだと実感しましたね」
人への信頼という点では、従来機『Color 1000 Press』運用時からのサポート対応の安心感が大きかったという。
「Color 1000 Pressを10年近く使ってきたので、修理が必要になることもありましたが、富士フイルムのエンジニアの方は、こまめに状況を見に来てくださって、“転ばぬ先の杖”で大きなトラブルになる前にメンテナンスしてくださるんです。これはとても心強いですよね。機械の状態をつねに把握していただいているという安心感もあります。この信頼関係は、長く使っていく上で非常に重要だと思います」
■特殊トナーの活用で、クリエイティブの幅が大きく広がる
Revoria Press PC1120導入から約3カ月。立ち上がりはスムーズで、すでに期待どおりのメリットを実感しているという。

Revoria Press PC1120で出力したオリジナルラベル
「PC1120のインターフェイスはColor 1000 Pressと同様にわかりやすいもので、オペレーションに不安などはまったくなく、導入してすぐに本格稼働に入ることができました。つい先日は、地元の銀行様からのご相談で、あるパーティーの記念品のお酒をご用意したのですが、書道家・涼風花先生の書をPC1120でオリジナルラベルとして出力し、150本ほど作成しました。印刷品質も生産性も従来機より上がっているので、このような依頼にも難なく応えることができます」
トータルで数万部という大ロット・バリアブルのDMなども、安定して効率よく出力できているという。
「高品質のものが早く安定して生産できるというのは、当たり前のことではありますが、電気代が高騰し、働き方改革にも力を入れている現在の状況では、その重要性がいっそう増しています。1枚目から同じ色をキープでき、紙詰まりなどで機械が止まることもないので無駄な時間や労力を費やすことがない。ごく基本的な部分ですが、当社にとっては大きなメリットです」特殊トナーの本格活用については、取材時点ではまだ準備段階であったが、井上社長は幅広い用途展開に期待を寄せている。
「ちょうど明日、富士フイルムさんが特殊トナーの勉強会を開いてくださることになっているんです。デザイナーたちに、データの作成方法などをレクチャーしていただきます。運用はこれからですが、いろいろと構想は練っています。たとえば、コロナ禍以降、クーポン券などのニーズが増えているので、シルバーやクリアなどの高精細出力を活かして、偽造防止印刷をお客さまに提案できればと考えています。バリアブルソフトの『FormMagic』も併用すれば、ナンバリングやバリアブルQRコードなども入れられます。小回りが利いて特色もバリアブルも自在に活用できるマシンというのが、Revoria Press PC1120の立ち位置。これからイベントが増えてくる中でさまざまな面白い提案ができるのではと期待しています」
構想は平面的な印刷物にとどまらない。立体的なオブジェクトなども視野に入っている。

IGAS2022で展示されたライティングオブジェ
「umbel」、ミウラ折りをアートへと昇華させた
作品でもある。
「昨年、『IGAS2022』の富士フイルムブースで、Color 1000 Pressで製作したインテリアのサンプル(ライティングオブジェ「umbel」)を展示させていただきましたが、このような立体物にもどんどんチャレンジしていきたいですね。昨年のサンプルは4色でしたが、PC1120でシルバーやゴールドを使えば、デザイン性、付加価値をさらに高められると思います。印刷は平面というイメージが強いですが、立体で、インテリアという機能があって、デザイン性も高い、そんな新しい印刷物をつくっていきたいと思っています」
■新たな付加価値提案、そして地域の活性化にもつなげたい
井上社長が大きな期待を寄せる新戦力、Revoria Press PC1120は、社内の活性化にも貢献しているという。
「導入機種を決める段階から社員に参加してもらったこともあって、皆、愛着を持ってくれていると思います。また、デザイナーやオペレーターなどの専門職のスタッフが長く勤める上でも、PC1120の導入はいい刺激になり、効果的だと思っています。特殊色が4色もあって、いままでなかなか考えられなかったような表現ができる。発想の幅が広がるので、現場の士気も上がっていますね。これが、お客さまへのいい提案にもつながるのではないかと期待しています」
さらに、井上社長は、Revoria Press PC1120の導入効果を、社内だけにとどめず地域全体にも広げていきたい考えだ。
2023.07.04
◆富士フイルムグラフィックソリューションズ Webポータルサイト「FCOS-Portal」をオープン ~資材発注の業務効率化、発注ミス削減に貢献~
富士フイルムグラフィックソリューションズ株式会社(代表取締役社長:山田 周一郎、以下FFGS)は、顧客の資材発注用のWebサイト「FCOS-Portal」(エフコスポータル)※1を8月より本格オープンする。
「FCOS-Portal」は、顧客が取引している「FCOS-Portal」加盟店※2に利用の申込みをすることで、日々の資材発注がインターネット上で可能となるサイト。また、発注できる商品はFFGSの取り扱い製品に限らず、加盟店が取り扱うさまざまな商品で発注が可能になっている。(取扱商品はお取引のある「FCOS-Portal」加盟店に問い合わせ)
FFGSでは今後、さまざまなメーカーや販売店とのコラボレーションをさらに進め、印刷業界における資材発注ポータルサイトの確立によりWeb発注の拡大を推進し、業務効率化と印刷業界のDX化に貢献していくとしている。
■発注の一元化による発注業務の効率化を実現
印刷工程の業務効率化やDX化が進む中、顧客が製造工程で日々使用される資材の発注においては、FAXや電話、口頭による発注など、現在もアナログ的な方法が中心となっている。FAXであれば送信漏れや、受信側の機器トラブル等による発注漏れの恐れがあり、また、電話や口頭による発注であれば発注履歴が残らないため、発注内容をお互いが誤認することによる受発注ミス発生の恐れがある。
さらに、これまでのWeb発注サイトにおいては、発注者が発注先ごとにサイトを切替える必要があり、発注業務が煩雑化し、一元管理が難しいという課題がある。
今回オープンする「FCOS-Portal」は、こうした課題の解決策の一つとして、顧客が「FCOS-Portal」加盟店と取引があれば、どの加盟店でも「FCOS-Portal」から発注ができるようになり、発注方法の統一や一元管理が可能となるため、顧客の発注業務の効率化を実現できるというもの。
※1 FCOS: FFGS Customer’s Order Site
※2 「FCOS-Portal」加盟店(2023年7月1日 現在) 敬称略 五十音順
IKCS株式会社、株式会社アセラ、株式会社一誠社、グラフィック機材株式会社、
合同印刷機材株式会社、株式会社江東錦精社、港北メディアサービス株式会社、株式会社ゴプス、
有限会社サン・メイト、株式会社ショーワ、株式会社信越ワキタ、株式会社シンクグロー、
株式会社真和、誠伸商事株式会社、株式会社タカノ機械製作所、株式会社中国インキ商会、
株式会社千代田サプライ、東洋インキ株式会社、内外インキ中国販売株式会社、
株式会社西岡弘英社、日本シー・アンド・シー株式会社、株式会社ハセベ、
文化総合印刷機材株式会社、株式会社吉田商会、リョービMHIグラフィックテクノロジー株式会社
【主な特徴・機能】
●取引している「FCOS-Portal」加盟店をサイト上で選択し、発注できる。
●過去の購入実績を元に、事前登録された商品の中から選択するだけの簡単操作。
●納品先と商品、数量の組み合わせでお気に入り登録できるので、定期的な発注はより簡単になる。
●発注情報のCSVインポート/エクスポート機能。
●在庫管理機能。
●スマートフォンやタブレットから発注が可能。
【「FCOS-Portal」活用メリット】
●簡単操作で、従来のFAXや電話発注よりも効率化が図れる。
●注文履歴が確認できるので、発注忘れや発注ミス等が低減できる。
●取引のある「FCOS-Portal」加盟店やメーカーであれば、どこにでも発注できるので、発注業務の一元化による効率化が図れる。
●スマートフォンやタブレットでも発注できるので、PCがない現場など場所を選ばず利用できる。
●取引先からの各種情報(お知らせ、商品発売通知等)がタイムリーに受け取れる。
同件に関する問い合わせは、下記より。
富士フイルムグラフィックソリューションズ株式会社 業務一部
TEL:03-6419-0327 FAX:03-6419-9890
〒106-0031 東京都港区西麻布2-26-30 富士フイルム西麻布ビル
2023.05.24
◆サイバーテック マニュアル作成支援システム「PMX」新バージョンをリリース
ITで企業のDX対応をサポートする株式会社サイバーテック(代表取締役社長:橋元 賢次 本社:東京都渋谷区、以下サイバーテック)は、DX推進にも寄与するマニュアル作成支援システム「PMX」のバージョンアップを行い、Version6.2の提供を開始致する(出荷開始日:2023年6月30日)。
国産のマニュアル用CMS製品としてサイバーテックが提供する、マニュアル作成支援システム「PMX」は、2022年2月にメジャーバージョンアップを行い、Version6.0をリリースした後、2022年7月1日にVersion6.1をリリースした。
今回のバージョンアップでは、今話題のChatGPTで活用されている、AI(人工知能)による自然言語処理技術をベースとしたニューラル機械翻訳との直接連携の実現や、コラボレーション機能の強化をはじめ、さまざまな機能強化がされている。また、ユーザーからのご要望にお応えする形で、数多くのオプションもリリース。これにより、スモールスタートによるリーズナブルなご利用も可能である一方、従来にも増して必要な機能のみを選択したマニュアル作成支援システムとして利用できるようになった。
<本件に関する問合せ先>
株式会社サイバーテック 管理部 広報担当:薮田
〒150-0044 東京都渋谷区円山町20-1 新大宗道玄坂上ビル7階
TEL:03-5457-1770 FAX:03-5457-1772
URL:https://www.cybertech.co.jp/ E-Mail:info@cybertech.co.jp
2023.04.19
◆サイバーテック マニュアル作成支援システム「PMX」試用プログラムを一新! ~並走型の手厚いサポートとともに、DX推進とマニュアル用CMSの普及促進に貢献
ITで企業のDXをサポートする株式会社サイバーテック(代表取締役社長:橋元 賢次 本社:東京都渋谷区、以下サイバーテック)は、このほど、DX推進にも寄与するマニュアル用CMSの普及活動の一環として、従来から存在したマニュアル作成支援システム「PMX」の試用プログラムを一新し、同時にWebサイトで広く募集を開始した。
※「PMX」無償試用プログラム募集用Webサイト https://www.cybertech.co.jp/xml/xmldb/pmx/pmx-trial/
マニュアルをとりまく環境は、一昔前のペーパレス化推進によるPDFを中心とした配信形態ではなく、Webマニュアル(HTMLマニュアル)によるユーザビリティの向上を目指す企業をはじめ、マニュアルの多言語化を進める企業、あるいは属人的手法から脱却するためにマニュアル作成の分業化を進めるといった企業が増加している。それらの課題解決には、マニュアル用CMS(コンテンツ管理システム:
サイバーテックでは、それらの懸念を少しでも解消し、CMSの普及促進に貢献するための活動として、このほどマニュアル作成支援システム「PMX」の無償試用プログラムを一新し、Webサイトで広く募集を開始することにした。
また、最新のトレンドである機械翻訳の有効活用にとどまらず、顧客ロイヤルティ向上やマーケティング
■マニュアル作成支援システム「PMX」試用プログラムの特徴
◎並走型による手厚いサポートで、無償にもかかわらず小規模PoCと同等の効果!
試用期間中はオンラインミーティングを3回準備しており、担当営業が並走する形でサポートする。また、質問票を活用して、操作時の不明点などを記録しながら試用を進めることが可能となり、実質的に無償で小規模PoCを実施する取り組みと同じ効果がある。したがって、マニュアル用CMSをはじめとするシステム導入の検討が初めてという企業も安心である。
◎豊富なオプションとテンプレートを試すことが可能!
試用プログラムでは、マニュアル作成支援システム「PMX」の標準機能とは別に、あらかじめ豊富なオプション機能も追加されている状態で利用できる。初期テンプレートも複数準備しているので、好きなテンプレートを選択し、豊富な機能を試用することが可能である。マニュアル用CMS導入には、どのような機能が必要かといった観点でオプションを試すことができる。
◎試用を行ったコンテンツは1ヶ月保存!
試用時に作成されたコンテンツは、試用終了後も1ヶ月間保存しているので、保存期間内でマニュアル作成支援システム「PMX」を本契約すると、試用時のコンテンツがそのまま利用できる。
■マニュアル作成支援システム「PMX」とは?
DTPソフトやMS Wordを使った属人的な制作フローではなく、ワークフローによるチーム・ドキュメンテーションを実現する、画期的な国産のマニュアル作成ツール。複雑な多言語マニュアルの作成~改訂運用も、コンテンツの標準化と共通化により、重複コンテンツの一元化を実現し、クオリティを向上させる。
変化に強いXMLデータベースでコンテンツを一元管理することにより、PDF組版とWebマニュアル出力をワンソースで出力可能。赤入れや手戻りが無くなり、制作業務のカイゼンによる効率化と配信スピード向上・翻訳コストの削減や、改訂時のヌケモレ防止による品質向上を実現する。
◎共同制作:権限設定とワークフローで役割を分担、テレワークにも最適!
マニュアル作成においてエンジニアの協力は欠かせない。「PMX」では、エンジニアへのライティング依頼~確認もスムーズに進めることができる。
◎多言語化:コンテンツの部品化と機械翻訳でリーズナブルに多言語展開!
多言語マニュアルの作成~改訂運用は非常に煩雑であるが、「PMX」ではコンテンツの部品化と共通化により、多言語マニュアルの作成~改訂運用の品質向上を実現している。機械翻訳やCATの活用により、スピーディかつ低コストで多言語マニュアルの改訂運用が行える。
◎組版と電子化:ワンソースからPDF組版と電子マニュアルを一括出力!
「PMX」では、コンテンツを一元管理しているため、HTML形式による電子マニュアルや自動組版による
■マニュアル作成支援システム「PMX」が向いているドキュメント
◎製造業
マニュアル全般(操作マニュアル・取扱説明書・サービスマニュアル)・規格票・技術標準文書・作業指示
◎ソフトウェア
ユーザーズガイド・リファレンスマニュアル・オンラインヘルプ・FAQ・運用保守マニュアル
◎金融・サービス業
業務マニュアル・事務規程集・契約書・報告書・オペレーションマニュアル・約款・規約
◎教育・出版業様
デジタル教材・プリント・副教材・問題集・学習参考書・定期刊行物・加除式書籍
■マニュアル作成支援システム「PMX」システム概要図
マニュアル作成支援システム「PMX」は、基本機能に加え、コンピュータ支援翻訳(CAT)ツールや、サイバーテックが提供する、AIによる校正支援(ゆらぎ検出)APIとの連携をはじめ、さまざまな外部ツールとの連携が可能。国内シェアNo.1のXMLデータベース「NeoCore」を内蔵することで、コンテンツの一元化と高速検索を可能である。
■マニュアル作成支援システム「PMX」基本機能一覧(※はオプション)
・XMLデータベースによる、多言語コンテンツ管理(トピック、マップ、素材、属性、バージョン)
・コンピュータ翻訳支援(CAT)ツールとのシームレス連携 ※
・素材データ管理(画像、動画、Excelファイル)
・トピック作成編集エディタ
・マップ構成編集(新規作成・改訂)
・Microsoft Word / FrameMakerデータの取り込み ※
・Adobe InDesign連携 ※
・Webマニュアル(HTMLアーカイブ)/ PDF / MS Word / XML による出力
・ワークフロー機能
・AI(人工知能)による、校正支援(ゆらぎ検出) ※
・セキュリティ/ユーザー管理/グループ管理/アクセス管理
■マニュアル作成支援システム「PMX」紹介ページ
マニュアル作成支援システム「PMX」を案内するWebサイトは以下から。
URL: https://www.cybertech.co.jp/xml/pmx/
サイバーテックは、DXの推進がますます進む今後の情報化社会において、企業内ドキュメントの革新的な
【問い合わせ先】
株式会社サイバーテック 管理部 広報担当 薮田
住 所:〒150-0044 東京都渋谷区円山町20-1 新大宗道玄坂上ビル7階
電 話:03-5457-1770
F A X :03-5457-1772
メール:info@cybertech.co.jp
W e b :https://www.cybertech.co.jp/
2023.03.23
◆富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ SUPERIA ZX導入事例――日経印刷株式会社 理想の完全無処理環境が実現し、製版・印刷両部門でメリットを実感 「視認性の高さ」「キズのつきにくさ」が安心感をもたらし、生産効率アップにも寄与
2024年に創業60周年を迎える日経印刷株式会社(本社:東京都千代田区飯田橋2-15-5/代表取締役社長:廣瀬 智氏)は、その大きな節目を前にした2022年7月、「刷版工程の完全無処理化」を達成した。テスト期を含め、およそ2年をかけてじっくりと進めた無処理プレートの導入プロセスには、どんな紆余曲折があり、結果的にどのような工程改革が成されたのか。製版部部長・松岡哲也氏と印刷部 G2 印刷1課課長・大森健一氏に、製版部門・印刷部門それぞれの観点から、SUPERIA ZX採用の経緯や、現場に生まれたメリットについて伺った。
■プレートセッター更新を機に、一気に無処理化への機運が高まる
個人経営の謄写印刷所『日経プリント』として1964年に創業して以来、冊子・書籍などページ物の仕事を中心に“こだわりの技術と信頼性”で着実に業容を拡大し続け、いまでは企画・デザインから仕分け・発送までワンストップで完結できる都内有数の総合印刷会社へと成長した日経印刷。出版・製薬・金融・各種メーカー等々、幅広いクライアントの多様な仕事を手がけ、中でも、国の行政機関である中央省庁が刊行する“白書”については「白書の日経」と異名をとるほどの実績がある。近年では、配信サポートや映像制作を主とした『NP CREATION』という新事業も展開し、印刷物とデジタルコンテンツの両構えでクライアントのニーズに応える同社だが、企業前進の原動力となっているのは、長年にわたり磨き上げてきた印刷技術である。

日経印刷のフラッグシップ工場『グラフィックガーデン』
その象徴、集大成とも言えるのが、2008年に竣工したフラッグシップ工場『グラフィックガーデン』だ。これにより、もともと 3カ所に分かれていた製造拠点が、このグラフィックガーデン(板橋区)と浮間工場(北区)の2工場体制に。そして、「印刷のエキスパートとしてお客さまのために何ができるのか」をさらに深く追究する、日経印刷の新たな挑戦が始まった。その挑戦の一つに「環境対応の再強化も含まれていた」と松岡部長は言う。
「環境負荷低減には早くから取り組んでいたのですが、グラフィックガーデンの開設を機に、よりいっそう徹底しようと。工場設計段階から排出物の抑制やリサイクルなどに徹底的に配慮し、綿密にデータを取りながら成果を高めていきました」
最新のデータを見ると、何とリサイクル率は97%。実際、グラフィックガーデンは、優れた環境対応設備や積極的な企業活動が認められ、2012年にグリーンプリンティング工場認定を取得。その後、「印刷産業環境優良工場表彰」で最高位となる経済産業大臣賞を受賞している。そして2021年。「製版工程廃液ゼロ」に向け、完全無処理化への取り組みが始まった。
「初期の無処理プレートが登場した頃からつねに注目し、何回かテストも行なっていました。ただこれまでは、環境性能は文句なしでも、実用面ではまだまだ発展途上の技術であると判断し、つねにアンテナを張りながら、意に適う無処理プレートの登場を心待ちにしてきたわけです」(松岡部長)
無処理化を推し進めるきっかけとなったのは、2020年、プレートセッターの更新だった。
「グラフィックガーデンのプレートセッター 3台のうち 2台が更新の時期を迎え、無処理プレート対応機に置き替えることになりました。浮間工場にある1台はすでに対応済みでしたから、これを機に両工場とも無処理化を進めようと。長い間、導入を見送ってきた無処理プレートでしたが、セッターの更新によって一気に機運が高まったんですね。早速、各社の最新プレートを比較検討した結果、総合性能の高さから『SUPERIA ZD-II』 を選択し、さまざまな絵柄、台数、通し枚数、所有している印刷機との相性などを徹底的にテストしました」
約半年のテストを経て、2021年5月、満を持して、無処理プレートの本格運用が始まった。

完全無処理化により「廃液ゼロ」「大幅な省スペース化」を実現した刷版室
■視認性の大幅アップで、「無処理」を意識せず使えるレベルに
製品性能をシビアに見極め、高いレベルでの活用にこだわる日経印刷の現場で、初めての無処理プレートはどのように評価されたのだろうか。松岡部長は当時の印象をこう語る。

松岡部長
「無処理プレートの中では最先端を行っていたSUPERIA ZD-II ですが、どうしても我々が求めてしまうのは、有処理と変わらないレベルのプレート性能なんですね。ですから現像工程がなくなることによる数々のメリットを実感しつつも、視認性や刷りやすさなどについては、まだまだこれから進化していく余地があると、次世代のプレートへの期待を抱きながらの運用でした」
現場は柔軟に適応し、わずか1カ月ほどで9割程度の仕事をZD-IIでこなせるようになったというが、それでも一気に「全面切り替え」は断行せず、しばらく慎重に有処理の『XP-F』との併用を継続。完全に自現機を撤去したのはおよそ1年後、2022年の夏だった。ちょうどこのタイミングで、無処理プレートをZD-IIから次世代の『SUPERIA ZX』へと移行した。
「7月に、グラフィックガーデンの残り1台のセッターを無処理プレート対応機に更新し、翌8月からすぐにSUPERIA ZXの本格運用を開始しました。この時点で100%完全無処理化が達成できたわけです。11月には浮間工場も含めて全社ZXで統一しました」(松岡部長)
ZXに移行したことで、現場の評価はどう変わったのか。印刷部の大森課長は、「まず感じたのは、視認性が格段によくなったこと」と語る。
「製版現場からも『すごく見やすくなった』という声がありましたが、印刷現場では、さらにインパクトが強かったように思います。初めに有処理のXP-FからZD-II に替わって慣れるのに苦労したあと、今度は一気に元の有処理のレベルに近づいたわけですから、非常に安心感がありますよね。実際、視認性の改良がZX開発の大きなテーマだったと聞いていますが、それも納得できる大幅改良だと感じました」
松岡部長が付け加える。
「XP-Fとまったく同じとまでは言えませんが、無処理プレートであることを意識せずに使える充分なレベルです。この版がどのジョブの何色の版なのかを、ストレスなく判別して作業を進められますから。視認性の向上は製版現場・印刷現場どちらにもメリットがある、最大の進化だと思います」
SUPERIA ZXは、製版現場だけでなく印刷現場にも恩恵をもたらしており、それは視認性の向上だけにとどまらないという。
「XP-FやZD-II と比べてもキズがほとんど発生しなくなり、版キズのトラブルはほぼ解消され、作業効率が確実にアップしています。以前は、キズが発生するとプレートを再出力したり消去ペンで処理したりといった作業がつきものでしたが、最近ではほとんどありません」(大森課長)
効率面で言えば、SUPERIA ZXは、刷り出しの早さも申し分ないレベルだという。
「ZD-II では、紙面にインキが乗るまでにそこそこの枚数を通していたのですが、ZXでは1枚目からインキが乗ってきます。また、地汚れが出にくくなった分、水目盛りを下げられるようになったので色の安定性も高まり、ドットゲインの振れ幅も以前よりかなり小さくなっています。色合わせも断然やりやすくなりました」(大森課長)

LED-UV機が並ぶ印刷現場。SUPERIA ZXは優れたUV適性を発揮している
■刷版工程自動化など、さらなる改革への足がかりに
最後に、SUPERIA ZD-II との比較ではなく、無処理プレート共通のメリットである「自現機レス」による効果について、松岡部長に総括していただいた。

大森課長
「2021年の導入時、最もインパクトがあったのは刷版室の省スペース化でした。もともとそれほど狭い部屋でもなかったのですが、実際に自現機を撤去してみたら『こんなに広くなるのか』と驚きましたね。自現機に付帯する機器も一緒に撤去したので、空きスペースがさらに広々と感じられました」
不要になったのは、自現機の「スペース」だけではない。
「実務上のメリットとして、定期的なメンテナンスの時間や手間がゼロになったことも大きいですね。また、現像廃液がゼロになることで直接的にコストの削減につながっていますし、現像液のマニュフェスト伝票を発行する必要もなくなりました。工場の環境対応レベルが一段とアップしたことも、会社として重要なメリットだと考えています」(松岡部長)
松岡部長は、もう一つ、現像工程カットによる「品質管理面でのメリット」を付け加えた。
「ゴミの付着、現像液の劣化による影響など、有処理ではどうしても現像段階でのトラブルのリスクがありました。厄介なのは、印刷でトラブルがあった場合、現像なのか、露光なのか、プレートそのもののせいなのか、原因の切り分けが難しいんです。いろいろな要素が絡んでくる。しかし無処理であれば、はじめから現像トラブルという要因を取り除けます。おかげで、万が一の際の原因究明がよりスピーディーに進められるようになりました」
自現機の設置スペースゼロ、廃液ゼロ、メンテナンスの負担ゼロ。そうして生まれた余力を、どのように活用していくのか。松岡部長は今後の展望も含めてこう結んだ。
「人に関しては、機器管理の負荷が減った分、他の生産的な作業に時間を使えるようになりました。省スペースについては、自現機 3台分の空間が増えたので、そこに新たな生産機を導入することも可能ですし、自動搬送装置などの設置によってプレート出力のオートメーション化に取り組むこともできます。無処理化をきっかけに、より効率的に、より高品質なものづくりが行なえるよう改革を進めていきたいと思います」
日経印刷はこれからも、「地球にやさしい」「人にやさしい」印刷会社として進化を遂げながら、クライアントの企業価値アップに貢献するべく、自らの革新に挑み続けていく。
2023.03.17
◆富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ tilia phoenix導入事例――大阪印刷株式会社 RPAツールとの連携でアクリル商品の面付けを自動化 多種多様なジョブの最適な付け合せパターンを瞬時に算出、人的ミスの削減にも寄与
同人誌印刷や各種グッズ製作を手がける大阪印刷株式会社(本社:大阪府大阪市此花区常吉1-1-60、代表:根田貴裕氏)は、工程自動化の一環としてジョブプランニング・面付けソフトウェア『tilia phoenix』を導入し、人手に頼っていたアクリルグッズなどのグルーピング・面付け作業の大幅な効率化を実現。強みの一つである小ロット・多品種への対応力に一段と磨きをかけている。導入の経緯や具体的な効果などについて、同社の緒方人志氏、長江優花氏に伺った。
■同人誌・関連グッズの小ロットニーズに応える
大阪印刷は、漫画やアニメの同人誌および関連グッズの製作を手がける印刷会社。2012年、同人誌の委託販売書店兼漫画喫茶という業態で創業し、2016年にPOD・無線綴じ製本ラインを導入して以降、着々と設備を拡充しながら、印刷・製本加工を主体とする現在の業態へとシフトしてきた。顧客の9割近くが個人顧客となり、受注はすべて『OTACLUB』というWebサイト経由でオーダーを受けているため、同社は営業部門を設けていない。売上については、全体の約3分の2が、冊子や名刺、ポストカードなどの紙製品で、3分の1がノベルティグッズとなっている。

長江氏
大阪印刷の強みの一つは、商品開発力。メインターゲット層のニーズを的確に捉え、社内でアイデアを出し合って独自の商品を生み出していく。そのラインアップは、冊子からクリアファイル、シール・ステッカー、カレンダー、アクリルグッズ、缶バッジ、パッケージ、ステーショナリー、バッグ、食器類まで、多岐にわたる。
「印刷用の商材を購入し、それに印刷してお渡しするという形ではなく、もっと広い視野で商品づくりに取り組んでいます。ありものの商材に印刷するのであれば、どの印刷会社でもできると思いますが、当社は一からモノを創り出すことにこだわっており、お客さまにはその点でご支持いただいているのではないかと思っています」(緒方氏)
もう一つの強みは、小ロット・多品種に柔軟に対応できる機動力。デジタル印刷機や各種加工設備を充実させ、外注に出さず内製にこだわることで、高品質・短納期での商品提供を実現している。
「小ロットで高品質なものを安く・速く提供できる体制を確立することで、同人誌やグッズづくりにチャレンジする方の登竜門的な存在になりたいと思っています。初めて印刷を頼もうというお客さまにとって、その第一歩が大阪印刷になるように。そのために“少ない数で、きれいに安くつくる”ということに、熱意をもって取り組んでいます」(緒方氏)
日々入ってくる膨大な種類・件数の小ロットのオーダーに、効率よく、間違いなく対応するため、同社は工程の自動化にも力を入れている。とくに重点的に進めているのが、入稿から製造(印刷・加工)までの上流工程の自動化だ。たとえば、入稿データのファイル名や解像度などをチェックし、自動で修正・警告を行なう仕組みを、社内で独自に開発。発注者とのやり取りを極力減らすとともに、データ作成ミスによって“意図しない仕上がり”になってしまうことを防いでいる。

Webサイト上で色見本を確認できる
「注文件数は、多いときで月に1万8,000件ほど。1日約600件。これだけのオーダーに対し、入稿データのチェックは基本的に1人で行なっています。また、ファイル名などの大枠のチェックを終えてから、白版やモアレなどの詳細なデータチェックを行なう工程があり、その部隊が6名。1人あたり60件から100件ほどのペースになります。自動化の仕組みがなければ、この量をこなすことはできません。多くの商品を安く短納期で提供するには、自動化が必須になるわけです」(緒方氏)
今回、tilia phoenixを導入したのも、こうした自動化の取り組みの一環だ。面付け工程も、人の判断を必要とし、作業負荷が大きくミスも起こりやすかった。
「面付けの自動化については、冊子類のフローを先行して、別のツールを使って進めていました。紙製品は面付けがパターン化しやすく、効果をすぐに実感できると考えたからです。実際、明確な効果が得られたため、次のステップとして、ノベルティグッズの面付け自動化に着手したわけです。そのためのツールとして着目したのがtilia phoenixでした」(緒方氏)
ノベルティグッズの中で、まず自動化対象として考えたのが、アクリルキーホルダー、アクリルスタンドなどのアクリル商品だ。月に1,500件ほど、個数にして約8万個のオーダーが入る。ほとんどが小ロットで、納期(発送希望日)も発注者によってまちまち。冊子のような定型物とは違い、サイズや形状もさまざまだ。しかも、使用するアクリル板には、なんと200種類以上ものカラーバリエーションがある。これは発注側にとっては大きな魅力だが、製作側においては、多種多様なオーダーをいかに効率よく仕分け、面付けするかが大きな課題となる。
「小ロットのものが多いので、1枚のアクリル板に複数のオーダーを付け合せて印刷することになります。膨大な種類のアクリル板に、納期別に付け合せていかなければならないので、そのグルーピングが大変でした。板の種類ごとにクリアファイルを用意して、そこに紙の発注書を入れていき、その中で納期の近いオーダーを組み合わせる…といったやり方をしていたのですが、慣れるまでは付け合わせの判断にすごく時間がかかっていました」(長江氏)
そんな面付け作業を自動化するツールとして、同社は2つの製品を検討。最終的にtilia phoenixを選んだ理由について、緒方氏はこう語る。

「このようなツールを自社のフローに組み込んで運用するには、細かいカスタマイズが必要になるので、社員が自分たちで勉強し、楽しみながら構築していけるものが望ましいと考えています。その点、tilia phoenixは、他のシステムとの連携なども含めた自由度が高く、そこが魅力的でした。もう一つのツールは、金額的に合わなかったということもありますが、カスタマイズをベンダー側に任せることになる点が、当社にはマッチしなかったのです」(緒方氏)
大阪印刷には、システム開発を手がけるSEが在籍しており、さまざまな自動化システムを自社で構築している。長江氏もそのメンバーの一人だ。tilia phoenix導入に際しては、すでに運用していたRPAツールと連携させ、自動で最適な面付けを行なうフローを、自らの手でつくり上げた。
「基幹システムから書き出された受注情報と面付け条件が書かれたCSV、そして入稿された印刷用データを、特定のフォルダに入れるだけで、アクリル板の種類や納期を考慮した最も効率的な面付け結果が得られるようになりました」(長江氏)
SEの視点から見たtilia phoenixについて、長江氏は「概要を一度理解してしまえば、非常に使いやすいツール」と評価する。実際、同社では、FFGSから半日間のトレーニングを1回受けただけでtilia phoenixを使いこなし、短期間のうちに自動化フローを組み上げてしまった。
これにより、面付け担当者の負荷が大幅に軽減されただけでなく、生産効率が格段に向上したことは言うまでもない。
「カラーアクリルの商品に関しては、以前は1日に10件ほどしか処理できませんでしたが、tilia phoenixでは何十件もまとめて処理できるようになっています。私自身、手動での面付けを経験しているので、自動化の効果の大きさは身をもって実感しています」(長江氏)
また、tilia phoenixによる自動化は、人的ミスの削減にも寄与しているという。
「カラーアクリル板には似たような色名があり、発注書を人の目で確認していたときには、指定されたカラーを見間違えるなどのミスが起きていましたが、自動化によりそのリスクがなくなりました。これは、アクリルの廃棄率の低減にもつながっています」(緒方氏)

大幅に省力化された
■魅力的な商品をフットワークよく提供し続けるために
緒方氏は、「tilia phoenixの活用範囲はもっと広げていける」と手応えを感じている。
「アクリル商品の他にも、紙コースターやダイカットシールなどにも活用を始めていますし、今後、缶バッジの面付けもtilia phoenixで自動化したいと考えています。面付けからプリント、カットまで自動化し、生産能力をさらに高めていく計画です」
小ロットに特化し、品質とスピードにこだわり、魅力的な商品を次々と生み出し続ける大阪印刷。現時点でも圧倒的なバリエーションを誇る商品ラインアップは、今後もまだまだ拡充していくという。工程の自動化は、そのための重要な基盤づくりなのだ。
「小ロットの商品を求められるお客さまに対して、フットワークよく高品質な商品を提供できることが当社の最大の強みだと思っています。この強みをさらに伸ばしていくために、もっと改善したいところもありますし、システムを一から組み直したいところもある。自動化の取り組みはこれからも続けていくことになると思います」(緒方氏)
2023.03.13
◆富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ 生産工程最適化事例――株式会社広済堂ネクスト プリプレス工程の自動化・見える化で、工数を半分以下に削減 大幅な生産効率アップにより、成長戦略に向けたリソースの再配分が可能に
広済堂グループで情報ソリューション事業を担う株式会社広済堂ネクスト(本社:東京都港区芝浦1-2-3、代表取締役社長:根岸千尋氏)は、重要課題として取り組んでいる生産工程改革の一環として、2020年、FFGSのサポートのもと、プリプレス工程の自動化・省力化・見える化に着手。新たな工程管理システムを中核に据え、スキルレスで効率的、かつ柔軟性に優れた生産環境を実現している。取り組みの経緯と具体的な効果、今後の戦略などについて、プリントソリューション事業部 生産本部 プリプレス部の部長・佐藤祐志氏、次長・吉田貴裕氏、製版課 課長・藤井大祐氏に伺った。



■全体最適に向けた工程改革に着手
広済堂ネクストは、1949年、「櫻井謄写堂」として創業し、72年に「廣済堂印刷株式会社」へと改名。90年代からは、業界に先駆けて培ってきたデジタル情報加工技術をベースに、IT分野にもフィールドを拡大し、印刷とITを2本柱として事業を展開してきた。99年に株式会社関西廣済堂と合併し「株式会社廣済堂」に。2021年10月、持株会社体制への移行に伴い、「株式会社広済堂ホールディングス」の100%子会社として「株式会社広済堂ネクスト」が設立。印刷・ITに加え、BPOサービスも含めた情報ソリューション事業を継承し現在に至っている。
生産拠点としては、出版印刷をメインとするさいたま工場(埼玉県さいたま市)、新聞印刷の有明工場(東京都江東区)、デジタル印刷に特化した入間工場(埼玉県入間市/NTT印刷・福島印刷とのシェア生産)を持つ。
今回、最適化の取り組みを行なったのは、さいたま工場。雑誌や書籍、コミックスなどの出版物を中心に手がけ、入稿から製版、枚葉・輪転印刷、製本加工、配本までの一貫体制を持つ主力拠点だ。同工場では、最新の生産設備を備える一方で、とくにプリプレス工程において、人手に依存した作業が多く、前後工程との情報連携も充分にとれていないなどの課題があり、昨今の小ロット・短納期ニーズに確実に対応するには思い切った工程改革が必要だったという。
「出版物のプリプレス工程には、定型作業がかなりあり、そこには多くの人手とコストがかかっていました。しかも、それらはお客さまから対価をいただきにくい部分。ですから、可能な限りタッチポイントを減らし、作業の負荷軽減・標準化を図るとともに、工程の見える化も進めることで、プリプレス全体の生産効率を高めようと考えたのです」(佐藤部長)
同社はすでにMISや印刷工程管理システムを導入するなど、デジタル基盤の整備を積極的に進めてきたが、生産工程全体の最適化のためには、プリプレスのさらなる効率化が不可欠だった。そこで、2020年、プリプレス工程最適化のプロジェクトが始動。関係するメーカーとの調整も含めた全体のサポートをFFGSが担った。プロジェクトのパートナーとしてFFGSを選んだ理由について、佐藤部長はこう話す。
「3社のベンダーさんに声をかけさせていただき、それぞれ、システム再構築の提案をいただきました。他のベンダーさんからは、ほとんど人手を介さずに製版処理が行なえ、自動で出力されるような仕組みの提案もありましたが、FFGSさんの提案は、従来の作業の流れを活かしながら、可能な部分を自動化していくというもので、私たちの意向に最もマッチしていたのです」
また、吉田次長はこう付け加える。
「今回のプロジェクトでは、オフセット印刷のワークフローや製版作業に関する知見があり、MISとプリプレス・印刷工程とのシステム連携などにおいても信頼できるパートナーが必要でした。その点、FFGSさんは非常に安心感がありますし、日頃から当社の仕事内容や課題も把握していただいているので、サポートをお願いすることにしました」

FFGSが提案したプリプレス工程の改革案は、既存のMISおよび印刷工程管理システムと連携させた「プリプレス用の工程管理システム」を新たに導入し、そこに面付けや検版などの機能を組み込むことで、人手による作業を自動化・省力化するというもの。作業の流れは従来工程を踏襲するが、使用するシステムを一本化し、前後工程と情報連携をとることにより、スキルレスで効率的に製版処理が行なえる環境を実現するという考え方だ。
実際のシステム設計にあたっては、FFGSの技術担当が広済堂ネクストの生産現場に入り、使用しているシステムやオペレーターの作業内容を詳細に調査。自動化可能な工程の洗い出しを行ない、受注から刷版出力までの26工程のうち14工程を自動化・省力化するという目標を設定。現場の意見・要望をヒアリングしながら、システムに求められる要件を整理し、具体的な仕様を固めていった。
「プリプレス工程特有のソフトウェアや作業内容がいろいろある中で、どの作業に人が必要で、どこを自動化できるのか、FFGSさんにアドバイスをいただきながら判断していきました」(藤井課長)
同社が目指したのは、完全なフルオートメーションのラインではなく、定型作業を可能な範囲で自動化・省力化しながら、作業指示の確認や出力結果の検版など、最低限必要なポイントで人を介在させることにより、柔軟性と効率性を高いレベルで両立させることだった。その背景について、吉田次長はこう説明する。
「出版印刷の場合、個々の作業は定型的なものが多いのですが、入稿物によって工程の流れが微妙に異なってきます。入稿後に急な仕様変更が入ることもあるため、さまざまなケースに対応できるよう、柔軟性を持たせる必要がありました。また、すべて自動で一貫処理してしまうと、万が一トラブルが起きた際の後戻りが大変なロスになってしまいますので、トータルの効率性を考えると、当社にとってはこの形がベストだったわけです」
新たなワークフローの中核となるプリプレス工程管理システムは、FFGSが広済堂ネクストの要望を取りまとめ、それを反映したオリジナルシステムとして、富士フイルムビジネスイノベーションが開発を担当。『Control Station』の名称で、2022年3月から実運用を開始した。
「工程管理システムとしてはかなり短期間で開発していただきましたが、この種のシステムにつきものの初期不良もなく、立ち上がりはスムーズでしたね。オペレーションについては、やはりまったく新しい作業環境になるので、約1カ月のトレーニング期間を設け、プロジェクトチームのメンバーがオペレーター一人ひとりに操作方法などを丁寧にレクチャーしながら定着させていきました」(佐藤部長)
こうした現場へのきめ細かいフォローの結果、運用開始の1カ月後には、主力商材である文庫系の仕事の約95%を新システムのフローに移行し、初期の目的をほぼ達成できたという。


主要なプリプレス作業がControl Stationの上で効率的に処理できるようになった。(左)
印刷工程管理システムでは、刷版出力のステータス確認が可能に(右)
新フロー運用開始から約1年。同社が目指していたオペレーションの負荷軽減・標準化・見える化といった効果は明確に表われている。
「これまで、面付けや検版などは専用のソフトウェアを使用していましたが、これらの機能がControl Stationに集約されたため、多くのジョブはControl Stationのブラウザ画面のみでプリプレス作業が完結できるようになりました。面付けに関しては、あらかじめテンプレートを用意しておき、製本仕様などの情報はMISからControl Stationに取り込む形にしています。ですからMISの情報に従ってテンプレートを選択すれば、専門知識やスキルがそれほどなくても正確に面付けが行なえます」(藤井課長)
オペレーションを特定の担当者に依存することがなくなり、属人化の解消にもつながっているという。もちろん、作業効率も大きく向上している。
「新しいフローでは、一つの作業にかかる時間が従来より短くなり、一人のオペレーターが複数の作業を同時並行で進められるようになりました。いくつかのジョブが重なっても、無理なくこなすことができます」(佐藤部長)
また、Control Stationの導入と同時に、刷版工程では、完全無処理版への全面切り替えを実施。自動現像機に関わる付帯作業を排除し、従来より大幅に少ない人数で回せる体制を整えた。
こうした複合的な工程改革によって、プリプレス工程全体で見るとオペレーターの工数は従来に比べて一気に半減し、残業時間は約3割減(昨年度実績)になっているという。さらに、作業指示などの紙でのやり取りをデジタル化した効果も大きいと吉田次長は強調する。
「人が口頭で伝えたり、紙で渡したりという不確実な部分がほとんどなくなったため、無駄な確認作業が削減できたほか、作業履歴も効率的に管理できるようになり、ミスの防止にもつながっています。こうしたメリットは、とくに管理者が強く実感していますね。私の感覚では、管理者の工数は7割ほど減っていると思います」
一方、今回の工程改革は、プリプレスのみならず印刷現場にもメリットを生み出している。以前から運用している印刷工程管理システムと、Control Station、MISを連携させたことにより、印刷工程管理システム上で下版状況(刷版出力のステータス)を確認することが可能になった。MISに入っている印刷スケジュールと、Control Stationから送られる実際の刷版出力の情報が、印刷工程管理システム上で把握できるため、印刷オペレーターは、次のジョブをどのタイミングで印刷できるかを確認しながら作業を進めることができるのだ。さらに、印刷オペレーターが印刷工程管理システム上で自ら版出力の指示を出すことも可能になり、刷版担当者の負荷軽減にもつながった。


刷版工程の見える化、作業指示の確実な伝達により、印刷現場の作業効率も向上している
■工程のさらなる「見える化」を目指す
広済堂ネクストがこのように生産工程の全体最適化に注力する背景には、短納期対応やコスト削減といった課題の解決にとどまらず、全事業を俯瞰した「リソースの再配分」を進めることで、会社としての強みをさらに伸ばしていくという成長戦略がある。今回約2年がかりで取り組んだプリプレス工程の最適化は、そのための基盤づくりの一環と言える。
「いま、出版物の需要が伸び悩み、人材の確保や諸資材・エネルギーのコストアップなど、さまざまな課題がある中で生き残っていくには、あらゆる無駄を極限まで排除していかなければなりません。同時に、無駄の削減によって生み出したリソースを再配分し、成長分野に投資していくことが重要です。成長分野というのは、お客さまにしっかりと寄り添って、印刷・ITといった当社のコア技術・ノウハウを組み合わせながら最適なサービスやプロダクトをタイムリーに提供し続けること。自動化・省力化の取り組みは、すべてそこにつながっていきます」(佐藤部長)
限られたリソースを最大限に活かすための工程改革。佐藤部長は、次のステップとして「生産工程全体の見える化」をさらに推し進める考えだ。
「営業からプリプレス、印刷工程まではある程度見える化できましたが、現状、印刷以降の工程との連携が充分にとれていないところがあります。生産工程全体を通してタイムリーに状況を把握できる環境を整えることによって、どこに無駄があるのか、課題を明確化し、さらなる改善を進めていかなければいけないと考えています」(佐藤部長)
同社の社名にある「ネクスト」には、「成長・発展・未来」の意味が込められている。クライアントと共に成長・発展していくための、未来を見据えた改革への挑戦は、これからも続いていく。
2023.03.09
◆サイバーテック テキストマイニング用AIの教師データ作成サービスを開始 ~英語圏となるフィリピンの自社オフショア拠点による、日英の教師データ作成も対応~
ITにより企業のDX化推進をサポートする、株式会社サイバーテック(代表取締役社長:橋元 賢次 本社:東京都渋谷区、以下サイバーテック)は、このほど、テキストマイニング用AIシステムの教師データ作成サービスを開始した。
DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が求められている昨今、AIを活用することによるビジネスモデル改革や業務カイゼンは進んでおり、社会へのインパクトは日増しに大きくなっている。そのような中、SNSで投稿された内容や口コミからの掘り起こし、アンケートに書かれた文章の分析、文章内のおおよその意味を判別するネガポジ判定や、論文などから必要とするテキスト情報を抽出するといった、テキストマイニングにもAIの活用が進んでいる。
さらに、自然言語処理技術も進んだ結果、Google翻訳に代表される機械翻訳の性能向上や、話題性の高いAIチャットサービス「ChatGPT」の登場など、コミュニケーション分野におけるAI技術の向上は目覚ましいものがある。これらのテキスト情報を扱うAIシステムでは、コーパス情報をはじめとする大量の教師データの準備が求められている。
サイバーテックでは、数年前にAIによるゆらぎ検出~ライティング支援エンジンを自社開発したことを皮切りに、フィリピンに有する自社オフショア拠点「セブITアウトソーシングセンター」にて、AIシステム向けのアノテーションサービス「セブ ハイスペック アノテーション」を提供してきた。今回リリースした「テキストマイニング用AIシステムの教師データ作成サービス」は、AIによるゆらぎ検出~ライティング支援エンジンでも必要とされた教師データ作成ノウハウをベースに、テキスト情報へのアノテーションサービスをリーズナブルに提供することになった。
特に、自社オフショア拠点「セブITアウトソーシングセンター」があるフィリピンは、公用語が英語であり、新興国の中でも非常に高い英語力を有する地域となっている。したがって、テキストマイニング用AIシステムに用いられる教師データは日本語に限らず、英語による論文や調査記事、英字新聞などといった、英語コンテンツを対象とした教師データ作成も可能である。
■DX推進に不可欠!「テキストマイニング用AIシステムの教師データ作成」の特徴
サイバーテックの「テキストマイニング用AIシステムの教師データ作成」サービスの特徴は次の3点となる。
◎公用語が英語のフィリピンで実施、高い英語読解力で学習データの品質にも直結!
英文に対するアノテーションを実施するうえで、しっかりとした英文の読解力は最低限必要となるが、同社が自社オフショア拠点を有するフィリピンは、高い英語力を有する人材が多数存在する。その中でもセブ島エリアはフィリピンの首都マニラと比較した場合、おおよそ3分の2の物価であるにもかかわらず、数多くの英語スクールが存在するとともに、オンライン英会話の講師が多く輩出される高い英語力を有する人材が豊富なエリアである。したがって、英語テキスト情報に対しても高品質かつリーズナブルなアノテーション作業を行うことが可能である。
◎在宅スタッフではなく、直接雇用の正社員による、安定したアノテーション品質!
アノテーション作業は、オフィスに出社している直接雇用の正社員が行うので、社内でFace to Faceによるコミュニケーションを取りながら、高品質のアノテーション作業を実施することが可能である。経験豊富なアノテーションマネージャが進捗管理やチェック体制の構築、指示書の作成や見直しなどを行い、アノテーション経験が豊富なメンバーで構成されたチーム体制での作業となるため、属人的な「バラツキ・誤差」を極力なくし、高品質なテキストマイニング向け教師データ作成を実現している。ちなみに、セブITアウトソーシングセンターには日本人も複数名在籍しているので、日本語のテキストを対象としたアノテーションも対応可能である。
◎ラボ型のメンバー固定で、プロジェクト並走型アノテーションもリーズナブルに可能!
一般的なアノテーション業務委託の形式でもリーズナブルにテキストマイニング用AIシステムの教師データ作成が可能であるが、セブITアウトソーシングセンターの経験豊富なアノテータースタッフやアノテーションチームごと、皆様の企業におけるアノテーション部門としてBynameによるラボ型の要員固定を行うことが可能である。これにより、大規模AIシステムのモデル構築と並走した形で学習データ作成体制を構築することや、長期プロジェクトでのさらなる品質向上とコストダウンを実現することが可能となる。
■DX推進に不可欠!「セブ ハイスペックアノテーション」の特徴
サイバーテックが提供する、AIシステム向けのアノテーション作業代行「セブ ハイスペック アノテーション」サービスでは、主に画像データを中心に、次のようなAIシステム向けの学習データ(教師データ)作成を実施してきた。
・ セグメンテーション~画像からの領域抽出
・ キーポイント付与~画像への特徴点付与
・ バウンディングボックス付与~画像からの物体認識
・ データセットの分類~クラシフィケーション
・ 学習データの拡張~データアーギュメンテーション
今後は、ドキュメントソリューション事業と親和性が高い「テキストマイニング用AIシステムの教師データ作成」サービスをラインナップに加えることにより、画像データセットに対するアノテーションに加え、テキストデータに対するAIアノテーションにもサービス対象範囲を広げることになった。これにより、サイバーテックは、AI分野をはじめ、さらに付加価値の高い自社製品・サービスを提供していく。
■「テキストマイニング用AIシステムの教師データ作成」サービス 紹介ページ
「テキストマイニング用AIシステムの教師データ作成」サービスをご案内するWebサイトは以下となる。
URL: https://www.cybertech.co.jp/ito/service/text-mining/
■「AIアノテーション・BPO」事業 紹介ページ
「AIアノテーション・BPO」事業をご案内するWebサイトは以下となる。
URL:https://www.cybertech.co.jp/ito/
サイバーテックは、企業の情報化投資において、高い費用対効果とDX対応を実現するソフトウェア製品とITサービスを企業の皆さまに提供している。今回の取り組みにより、得意とするドキュメンテーション分野と、英語圏オフショアの強みを活かしたAIアノテーションサービスを拡充させることで、ユーザーのDX推進のサポートをしている。
<同件に関する問い合わせ先>
株式会社サイバーテック 管理部 広報担当:薮田
〒150-0044 東京都渋谷区円山町20-1 新大宗道玄坂上ビル7階
TEL:03-5457-1770 FAX:03-5457-1772
URL:https://www.cybertech.co.jp/ メール:info@cybertech.co.jp
2023.03.02
◆モリサワ MORISAWA PASSPORTなどのフォントサービスが第22回「佐藤敬之輔賞」企業団体部門を受賞
株式会社モリサワ(代表取締役社長:森澤彰彦 本社:大阪市浪速区敷津東2-6-25 Tel:06-6649-2151 代表、以下モリサワ)は、長年提供しているフォント製品「MORISAWA PASSPORT」やその後継サービスである「Morisawa Fonts」の功績が認められ、NPO法人日本タイポグラフィ協会による第22回佐藤敬之輔賞(企業団体部門)を受賞した。
佐藤敬之輔賞は、タイポグラフィに関する革新的な提言、研究発表、デザイン教育などで活躍された佐藤敬之輔氏を賞名とし設置された賞で、タイポグラフィの分野で活動する個人・団体に贈られるものである。
受賞したフォントサービスの一つであるMORISAWA PASSPORTは、2005年に提供を開始したフォントのサブスクリプションサービス。多様なフォントが定額で使い放題になるMORISAWA PASSPORTは、異なる会社同士での制作データの伝達を容易にし、新しいフォントロイヤリティのモデルケースを示した。
また、教育現場に向けた「アカデミック版」の提供や、文字組版の特別出張授業、FONT SWITCH PROJECTにおける交流・情報発信など、デザインの未来を担う若い世代への文字教育活動が評価された。MORISAWA PASSPORTはこの18年間、時代とともにさまざまな付加価値を模索し続け、自由な表現に欠かせないツールとして、新しいクリエイティブ制作に寄与してきた。書体ラインナップは当初の約200書体から、現在では多言語やユニバーサルデザイン(UD)フォントを含む1,500書体を超えている。
MORISAWA PASSPORTの製品は後継サービス「Morisawa Fonts」へと段階的に役割を引き継ぎ、2028年度までに終了を迎える予定である。Morisawa Fontsは、デバイスに依存しないユーザー単位のライセンスで利用できるクラウド型のフォントサービスとして、テレワークなどが浸透した現代の働き方にも対応した新しい製品である。モリサワは今後もユーザーの声に寄り添ったより良いサービスを目指し、豊かな文字コミュニケーションの発展に貢献している。
https://morisawafonts.com/
●同件に関する問い合わせ
株式会社モリサワ 東京本社 ブランドコミュニケーション部 広報宣伝課
SNSでも最新情報を公開している
Twitter:@Morisawa_JP
Facebook:@MorisawaJapan
※記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標である。